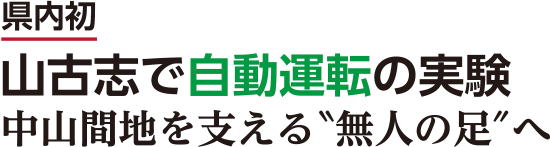|
| 国を中心に進めている、中山間地の人流・物流の確保を目的とした自動運転サービスの実験を3月17日から1週間、山古志地域で行いました。 国は平成29年度から全国の道の駅などを拠点に実験を進めています。市は、高齢者の診療所や買い物などへの移動、地場産野菜の運搬・集荷など、生活の足の確保を目的に、実験に応募。県内初の実験地に選ばれました。 実験ルートは、「やまこし復興交流館おらたる」から油夫(ゆぶ)地区を結ぶ約3km(下図)。車両は道路に埋められた電磁誘導線の磁力で進路を感知し、時速約12kmで走行します。 試乗した磯田市長は「中山間地の課題を解決できるだけでなく、観光客の移動手段としても活用でき、交流人口の拡大が期待できます。自動運転をはじめとする先進的な技術を積極的に取り入れ、市民の暮らしをより良くしていきたい」と語りました。 【問】交通政策課TEL39・2267 |
 実験で使用した6人乗りと荷台付き4人乗り(下)の車両。 道路中央の黒い部分が電磁誘導線 |
 |
 |
 |
日本文学者で、「米百俵の精神」の普及啓発に貢献した長岡市国際親善名誉市民・ドナルド・キーンさんが2月24日、逝去されました。96歳でした。 キーンさんは平成10年、文豪・山本有三が執筆した戯曲「米百俵」を英訳し、一冊の本「One Hundred Sacks of Rice( ワン ハンドレッド サックス オブ ライス)」(左写真)にまとめました。その後、英語版を基にホンジュラスやバングラデシュで、同国の劇団が公演するなど、教育・人材育成の重要性を説いた「米百俵の精神」を広く世界に伝えるきっかけとなりました。 本の中でキーンさんは「私自身が教育者として生涯を過ごしてきただけに、大きな障害を乗り越え、長岡の将来のためには教育が不可欠であるという結論に達した米百俵の逸話に、大きな感銘を受けた」とつづっています。また、歴史や偉人などにも興味を抱き、長岡に何度も足を運んでいました。 ドナルド・キーンさんのご冥福を心よりお祈りします。 |
 平成10年6月15日の「米百俵デー 市民の集い」で講演 |
|
|
| 上へ |